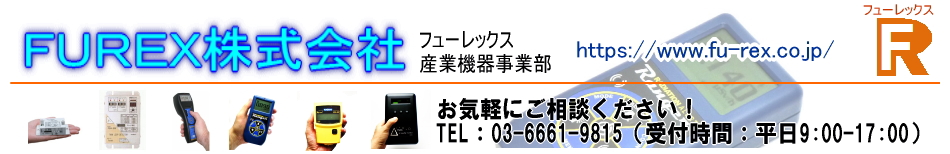ループコイル式車両検知器は、1960年代から1970年代にかけて交通管制の一環として導入が始まりました。特にアメリカやヨーロッパでは、信号制御や交通量計測の目的で広く普及しました。日本では1990年代から、地面に埋め込むことで邪魔にならず耐久性も高いという特長から、コインパーキングの車両検知装置として数多く使用されてきました。
起源と発展の流れ
- 1950年代〜1960年代
地中に埋設したコイルに電流を流し、車両の金属によるインダクタンス変化を検知する方式が確立しました。
- 1960年代後半〜1970年代初頭
交通量の増加に伴い、信号制御の自動化が求められるようになり、地中に埋設するループコイル式検知器が登場しました。磁界変化を利用するこの方式は、他のセンサー方式(光学式・超音波式)に比べて耐候性と精度に優れていたため、都市部の交差点や高速道路で採用が進みました。
- 1980年代以降
検知精度の向上や設置技術の標準化が進み、交通管制システムの中核として定着。日本でもこの頃から本格的に導入され、速度違反取締装置などにも応用されました。
- 1980年代後半〜1990年代初頭
日本では都市部を中心に土地の有効活用としてコインパーキング(時間貸し駐車場)が登場。初期は人力管理や簡易的な機械式ロック装置が主流でした。
- 1990年代中盤
駐車場の無人化・自動化が進み、車両検知のためのセンサー技術が求められるようになります。 ループコイル式検知器は、車両のみを検知し誤検知が少なく安価で信頼性が高いことから急速に普及しました。
- 2000年代〜現在
逆走検知や交通量計測、スマートシティ連携など、応用範囲が拡大。AIやクラウドとの連携によって、より高度な交通管理が可能になっています。
カメラとの連動などカメラ監視式コインパーキングでも数多く使われています。
地中に埋設したコイルに電流を流し、車両の金属によるインダクタンス変化を検知する方式が確立しました。
- 1960年代後半〜1970年代初頭
交通量の増加に伴い、信号制御の自動化が求められるようになり、地中に埋設するループコイル式検知器が登場しました。磁界変化を利用するこの方式は、他のセンサー方式(光学式・超音波式)に比べて耐候性と精度に優れていたため、都市部の交差点や高速道路で採用が進みました。
- 1980年代以降
検知精度の向上や設置技術の標準化が進み、交通管制システムの中核として定着。日本でもこの頃から本格的に導入され、速度違反取締装置などにも応用されました。
- 1980年代後半〜1990年代初頭
日本では都市部を中心に土地の有効活用としてコインパーキング(時間貸し駐車場)が登場。初期は人力管理や簡易的な機械式ロック装置が主流でした。
- 1990年代中盤
駐車場の無人化・自動化が進み、車両検知のためのセンサー技術が求められるようになります。 ループコイル式検知器は、車両のみを検知し誤検知が少なく安価で信頼性が高いことから急速に普及しました。
- 2000年代〜現在
逆走検知や交通量計測、スマートシティ連携など、応用範囲が拡大。AIやクラウドとの連携によって、より高度な交通管理が可能になっています。
カメラとの連動などカメラ監視式コインパーキングでも数多く使われています。
なぜループコイルが選ばれたのか?
- 高い検知精度:金属体積・車高・進入角度に応じた反応が可能
- 耐環境性:雨・雪・光に左右されにくい
- 長寿命・低メンテナンス:埋設型で故障が少ない
- 耐環境性:雨・雪・光に左右されにくい
- 長寿命・低メンテナンス:埋設型で故障が少ない
日本国内におけるループコイル式車両検知器の年表
| 年代 | 主な出来事・技術動向 |
|---|---|
| 1970年代 | 都市部の交通量増加に伴い、信号制御の自動化が進む。ループコイル式検知器が一部交差点で試験導入され始める。 |
| 1980年代 | 交通管制センターの整備により、主要都市で本格導入。速度違反取締装置や信号連動に活用される。 |
| 1990年代 | コインパーキングの無人化・自動化を目的に、信頼性の高さと安価なことから検知器としてループコイル式が採用され始める。 ETC構想が始まり、車両検知技術の精度向上が求められ、ループコイル式が採用される。 |
| 2000年代前半 | 駐車場や商業施設での車両誘導に活用が広がる。逆走検知・交通量計測などの応用機能が登場。 |
| 2010年代 | カメラによるナンバープレート認識技術が進化し、ロック板やゲートを使わない「ロックレス式」コインパーキングが登場。
カメラ式の課題である誤認識や入庫・出庫のタイミング判定の誤差を改善するためにループコイル式車両検知器が併用されるようになる。 地方自治体によるスマート交差点の整備が進み、AI連携やクラウド型交通管制との統合が始まる。 |
| 2020年代 | 自動運転車との連携を視野に入れたセンサー群の一部として再評価。既設ループコイルのデータ活用が注目される。 |
補足:国内導入の特徴
・都市部から地方へ:東京・大阪などの大都市圏から、地方都市や観光地へと導入が広がった。
・官民連携:国土交通省の交通管制事業と、民間駐車場・商業施設のニーズが融合。
・長寿命設計:国内では耐久性を重視した設計が多く、20年以上稼働する事例も。
・官民連携:国土交通省の交通管制事業と、民間駐車場・商業施設のニーズが融合。
・長寿命設計:国内では耐久性を重視した設計が多く、20年以上稼働する事例も。